幼いころ、ぼくはシャーロック・ホームズに憧れていた。
物語の冒頭、服装から得られるわずかな手がかりだけでワトソンの近況を言い当てたときは、子供ながら「すげー」と思ったのをおぼえている。
なぜホームズにそんな芸当ができたかといえば、彼が物事をよく観察していたからだ。
ただ見るのではない。つぶさに観察し、なぜそうなったのか仮説を立て、推論を組み立てていく。そうした一連の流れを自然にできたからこそ、彼は優れた探偵だったのだ。
シャーロック・ホームズのようになりたい。彼のような観察眼を持ちたい。そんな夢を抱いたものの、どうすればいいのかなんて当時のぼくにわかるはずもない。
結局、ぼくはホームズにはなれなかった。
あれから十数年。時は流れ、かつて抱いた夢はすっかり過去のものとなった。しかし、こうしてブログを書くようになったことで、ぼくは再び観察力というものに興味を持ちはじめた。
ブログを書いている以上、読まれたいという欲求は当然ある。では読まれるためにはどうすればいいのか考えたとき、必要だと思ったのが、ホームズのような観察力だ。
ブログだけに限らない。仕事でも創作でも、優れた観察力を持つことは重要だろう。優れたインプットができれば、よりよいアウトプットができるようになるはずだ。
ぼくは再びホームズを目指すため、『観察力の鍛え方 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか』を手に取った。
観察サイクルをまわす
どのように観察力を鍛えたらいいのか。その答えは、かなり早い段階で示される。
いい観察は、ある主体が、物事に対して仮説をもちながら、客観的に物事を観て、仮説とその物事の状態のズレに気づき、仮説の更新を促す。
『観察力の鍛え方 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか』19ページ
一方、悪い観察は、仮説と物事の状態に差がないと感じ、わかった状態になり、仮説の更新が止まる。
たくさんの情報と道具が現代社会にはあふれている。そういうものを全て一度手放し、仮説だけを武器にする。それが観察力を磨く方法だ。
『観察力の鍛え方 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか』55ページ
いい観察は、「問い→仮説→観察」のサイクルをまわすことで生まれる。解きたくなる「問い」と検証したい「仮説」があるからこそ、熱量のある「観察」がはじまる。
著者が特に注目するのは「仮説」だ。雑でもいいから「仮説」を立てると、サイクルがまわりやすくなると語る。
本書では、ヨハネス・フェルメールが描いた絵画『牛乳を注ぐ女』を例に挙げ、キューピッドの存在から「女は誰かに恋をしているのではないか?それとも、女は誰かに恋をされている?」という仮説を立てている。
とはいえ、いきなり仮説を立てろと言われても難しい。すぐにできたら誰も苦労しない。そこでいくつか具体的な方法が紹介されるわけだが、その中で個人的に一番印象に残っているのが、ディスクリプションだ。
ディスクリプションとは、自分が見たものをそのまま言葉に置き換えていくことを言う。
「なんだそんなことか」と思うかもしれない。しかし、ふだんのぼくたちは「見ているようで見ていない」ことがあまりに多い。なんとなく見ただけでわかったつもりになってしまい、それ以上、見ることをやめてしまう。あなたにも思い当たる節があるのではないだろうか? ぼくはたくさんある。ありまくりだ。
たとえば、ぼくは長年『パズドラ』をやっているが、モンスターのイラストを観察したことが一度もない。キャラクターだけをなんとなく見て、かっこいいな、かわいいな、ぐらいの感想を抱いて、それでおしまい。キャラクターのほかにどんなものが描かれているのか。なぜ描かれているのか。まるで考えたことがなかった。

アマテラスオオカミのイラストに三種の神器(勾玉と鏡、そして剣)が描かれていることを、恥ずかしながら最近になって知った。
ディスクリプションは、こうしたわかったつもりを防いでくれる。見たものを言葉にしなきゃいけないから、自然と細部にまで目が行き届く。得られる情報が多くなれば、それだけ仮説も浮かびやすい。
あいまいのすすめ
人はわかりたい生き物だ。わかった状態が望ましいと感じる。当然だろう。わからないままだと不安になる。勉強や仕事であれば、そもそもわかることが当たり前だ。わからなければ話にならない。
しかし、著者の考えは違う。「わかる」とそこで思考が停止してしまうから、「わからない」状態にい続けることが大切なのだと説く。わかったように感じても、そこで立ち止まらず、新たな問いを持ち、観察する。いつまでもわかった状態がこない、そんなあいまいさを受け入れる。そうすることで、新たな世界が見えてくるのだ、と。
突然なにを言いだすんだ? と思ったけど、時間をおいてみたら、著者の言わんとしていることがわかったような気がする。つまり、わかる状態になったと思ってもそれはあくまで暫定的なものであり、そこで考えを止めるな、ということだろう。たぶん。
仕事で言えば、いまのやり方を愚直に続けるのではなく、「もっと効率的な別のアプローチがあるのではないか?」と常に考えるべき、といったところか。
確かに、なにも考えないでいるのはストレスがなくて居心地がいい。逆に、もっとほかにいい方法があるのではないかと模索し続けるのは大変だ。
観察を続けること、すなわち問いと仮説を無限ループさせることの難しさを実感する。
最後に
子供のころは好奇心の赴くまま行動していた。あれはなんだろう。これはどういうことなんだろう。毎日、なにかしらの問いを持っていた気がする。
ところが大人になり、好奇心が働かなくなった。心が引かれない。問いを見つけて仮説を立てても、「どうせそんなこと知ったところでぼくの生活には1ミリも役立たねーし」と思った瞬間、一気に冷める。それ以上考えることをやめてしまう。生きていくためにはほかに考えなければいけないことがたくさんあって、好奇心を優先させている場合ではないからだ。
ぼくが最後に観察らしいことをしたのは、道端に生えている野生の草花の名前を知ろうとしたときだろうか。あのとき、ぼくははじめて道路の隅に生えている雑草の名前や葉の形を知った。これまで何度も目にしていたはずなのに。
著者も指摘しているが、観察するには時間が必要だ。時間、すなわち暇。スケジュールがみちみちに詰まっていたら、「まずは問いを見つけて~、それから仮説を立てて~、検証のために観察して~」なんてことをしている余裕はない。
タイパやコスパなんて言葉がもてはやされているいま、いかに時間をかけて観察ができるか。なかなかハードルの高い話だが、「わかる」ことの価値が低くなってきている世の中だからこそ、あいまいさを受け入れることの大切さを忘れないようにしていきたい。
いつか、ホームズのようになれると信じて。
なお、去年の暮れ、本書の改訂版が発売された。加筆部分があるということなので、いずれこちらも読んでみたい。新書の倍近い値段するけど。
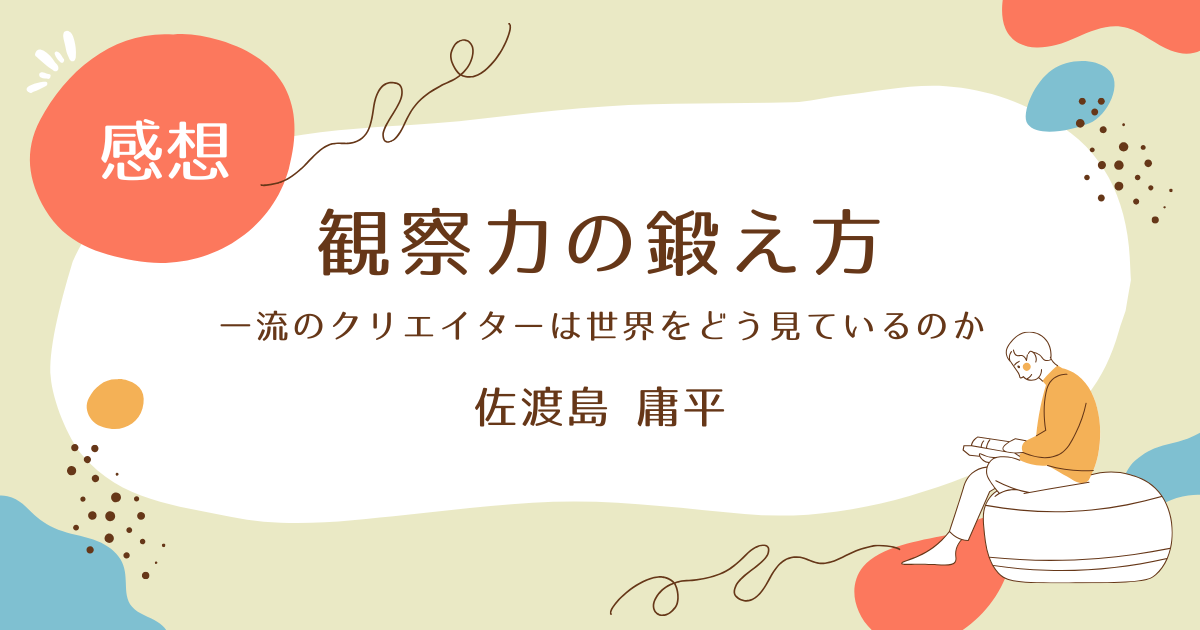




コメント