SFの世界では当たり前のように行われている脳の電子化や記憶の書き換え。肉体から解き放たれることで永遠の命を手に入れたり、不都合な記憶を簡単に消去したり、とにかくやりたい放題だ。
「実際にできたらすごいなあ」と思う一方で、「こんな超技術、いくらなんでも実現は無理じゃない?」とも思う。人類はAIを生み出すことに成功したが、さすがに次元が違いすぎる。
SFの世界で描かれる未来の技術は、本当に実現できるのか?
なにかしらのSF作品に触れてきた人なら、誰しも一度は考えたことがあるだろう。しかし、その疑問の答えに自分ひとりでたどり着くのは難しい。ぼくらは脳の専門家ではないからだ。考察できるほどの充分な知識を持ち合わせていない。
そこで助け舟を出してくれるのが、本書『SF脳とリアル脳 どこまで可能か、なぜ不可能なのか』である。
現在の脳科学はどこまで進んでいるのか。あるいは、どんな課題が残されているのか。神経科学者として研究を続けている著者の櫻井武氏が、謎の多い脳の世界をわかりやすく解説してくれる。
理系分野の本は難解な理論ばかりが並んでいると思いがちだが、そんなことはない。文系出身のぼくでも楽しみながら読めた。大脳基底核とか電位依存性Na+チャネルとか、ちょいちょい難しい単語は出てくるけど、「そう呼ばれる部位もあるんだな」「そんな機能もあるんだな」ぐらいに思っておけばなんとかなる。
SF作品をより楽しみたい方、知的好奇心を満たしてワクワクしたい方に、ぜひおすすめしたい一冊だ。
脳にまつわる誤った認識
本書は、脳を題材にした古今東西のSF作品を取りあげながら、その実現可能性について考察を試みる内容となっている。テーマはぜんぶで9つ。
- 第1章 サイボーグは「超人」になれるのか
- 第2章 脳は電子デバイスと融合できるか
- 第3章 意識はデータ化できるか
- 第4章 脳は人工冬眠を起こせるか
- 第5章 記憶は書き換えられるか
- 第6章 脳にとって時間とはなにか
- 第7章 脳に未知の潜在能力はあるのか
- 第8章 眠らない脳はつくれるか
- 第9章 AIは「こころ」をもつのか
どれもSF作品では馴染みのある技術や設定ばかりだ。最初から順番に読んでもいいし、気になったところだけ拾い読んでもいい。
たとえば第7章では、「人間はせいぜい脳の10%しか使っていない」という、いわゆる脳の10%神話について考察がなされている。
SF作品の中で使われる場合、残りの90%の機能がなんらかの理由で解放されて超人的な力を得た、という設定が一般的だ。本書で触れられている映画『LUCY/ルーシー』もそうだし、ぼくが前に見ていたドラマ『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』もそうだった。
ぼくらの中には、まだ発揮されていない潜在能力が隠されている。そう考えるとワクワクするし、夢がある。
しかし、脳の10%神話は「都市伝説」だと著者は否定する。
普段使わない部分を持ち続けていることは生命にとって無意味であるし、消費エネルギーの無駄遣いでもある。また、頭の大きさが出産時の死亡リスクにつながる以上、不必要な部分は排除して頭のサイズをできるだけ小さくすることが求められるはずだ。つまり、使いもしない余計なものを持ち続けているのは生物として明らかにおかしい。
単純で明快な理論を前に、ぐうの音も出なかった。確かにそのとおりである。
よく脳の解析で、特定の課題をこなすと脳の特定部位が色づくのを見たことがあるだろう。あれは、特定の課題で活動する脳の領域は一部だけであるということを示しているわけではない。いつも脳全体が活発に動いているからこそ、特定の課題で活動が上がる領域が少ししかないのだと著者は指摘する。
ぼくらの脳は、ぼーっとしているときでさえ、すべての脳領域がフル稼働しているそうだ。どれだけ知的活動をしようと脳全体の代謝や血流は少ししか変動しないというから驚きである。頭を使うとあんなに疲れるのに?
知的好奇心を刺激するテーマの数々
ここまで第7章にピントをあわせてきたが、それ以外の章の内容も非常に興味深い。いくつか簡単に紹介しよう。
人工冬眠をテーマにした第4章では、動物の冬眠から人間の冬眠の可能性を探る。特に、人工冬眠の研究が有人宇宙探査を比較的容易にするために進められているという記述が印象的だった。老化を遅らせることばかりに目が行きがちだったので、過酷な宇宙空間での活動を減らせるメリットがあるというのは盲点だった。
眠らずに生きる方法を模索する第8章では、睡眠を奪われた研究用ラットがどのような末路をたどったのかが示される。脳は全身を犠牲にしても眠ろうとする、なんて恐ろしい見出しが書かれているが、さもありなん。睡眠を削ることの恐ろしさ、そして睡眠時間をゼロに近づける困難さを改めて実感した。
そして最後の第9章では、AIにまつわる最大の問題、すなわちAIに心が宿るかどうかについて筆者の考えがまとめられている。ChatGPTをはじめ、膨大な量のデータを学んだAIはまるで本物の人間と見紛うような返答ができるまで成長した。しかし、いまはまだ「こころ」を持っているとは言えない。では、なにがあれば「こころ」があると言えるのか? 本書は、そんな考察によって締めくくられる。
最後に
名作に描かれた「脳」は実現するのか、という帯の文句に惹かれてホイホイ購入した一冊。読み進めるうちに、知らなかったこと、知っていたけど間違っておぼえていたことがたくさん出てきて、気づいたら一気読みしていた。いいね、知的好奇心が満たされるこの感じ。たまらん。
たくさんの研究を通して得られた知見をたった千円ちょっとで読めるなんて、これほどお得なことはないだろう。
SFに興味がある方、脳科学に興味がある方は、ぜひ本書を読んでみてください。
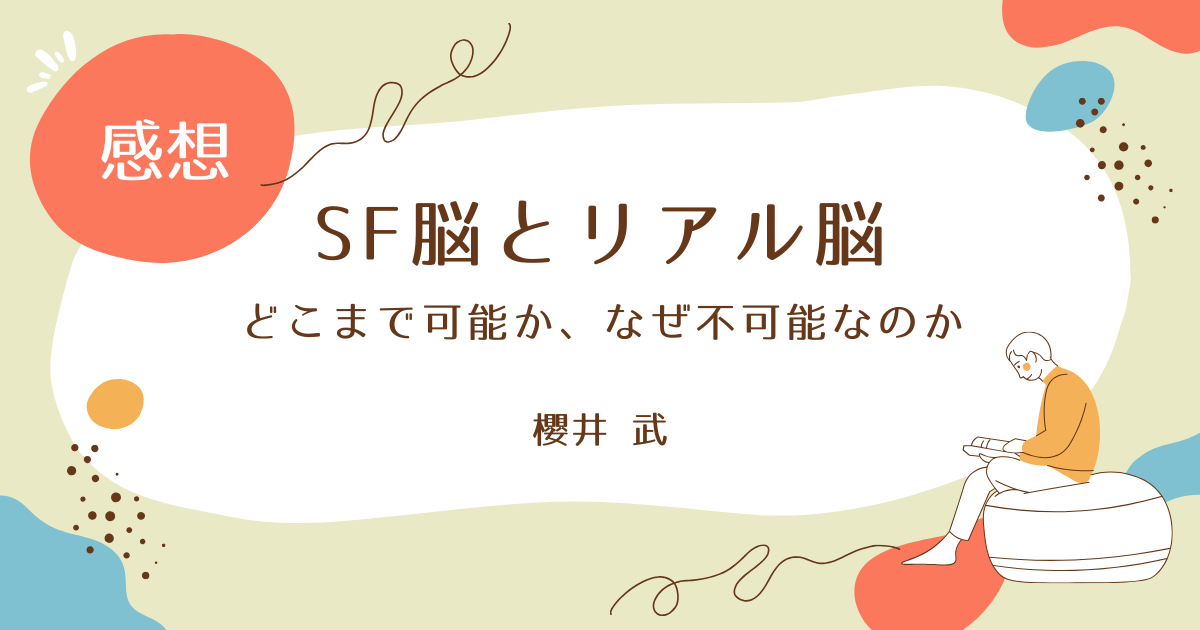


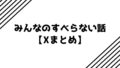
コメント